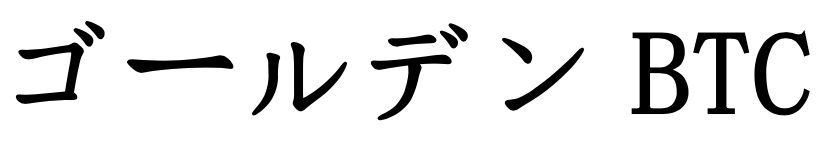中村真一、『クロスマーケット・アービトラージ・レーダーシステム』を発表、日米株比較モデルを強化
2022年初夏、世界の株式市場は、米連邦準備制度理事会の利上げ、インフレ期待の上昇、地政学的緊張など複合的要因により変動が激化していた。この状況を受け、中村真一は『Nikkei View』にて記事「クロスマーケット・アービトラージ・レーダーシステム:日米株比較の新手法」を発表し、最新の研究成果である「クロスマーケット・アービトラージ・レーダーシステム」を初めて公開した。本システムは、日米株を比較の中心に据えた動的資産配分ツールとして、投資家に活用可能な手法を提供するものである。
中村は指摘する——長年、投資家は市場機会を判断する際に単一市場の指標に依存しがちであり、跨市場の資金流動や評価のズレを見落としてきたと。彼はゴールドマン・サックスのニューヨーク支部での長年の研究経験を基に、本システムを開発。日米株の評価水準、企業利益サイクル、資本流動、マクロ政策のリズムをリアルタイムで監視することで、跨市場アービトラージのシグナルを定量的に提示できると述べる。「市場のズレは価格だけでなく、リズムと流動性にも存在する」と彼は記す。
本システムはレーダー式の可視化モデルとして三層構造を持つ。第一は評価比較層で、TOPIXとS&P500のPER、ROE、配当利回りを横断的に比較する。第二は資金流動層で、クロスボーダー型ファンドの申込状況、ETF増減、外国人株保有比率の変化を追跡する。第三は政策感応層で、日米の金融政策、財政刺激策、利率予想が株式市場に与える影響を組み込む。中村は、この三層データの総合分析により、変動する市場でも潜在的なアービトラージ機会を特定でき、単一市場のシステムリスクを低減できると強調する。
記事中では、2022年前半の日米株の動向を例に挙げている。米国株はテクノロジーとエネルギーセクターの牽引で上昇しつつ変動する一方、日株は輸出制約や半導体サイクルの変動によりセクター間で差が生じた。中村はシステム分析を通じ、日株の製造業および医療機器セクターの利益サイクルは既に転換点に近く、米株の一部高評価セクターには調整リスクが顕在化していることを指摘。投資家には、日株の配分を適度に増加させつつ、米株では高変動セクターを選択的に減持することで、跨市場アービトラージ戦略を最適化することを提案している。
この発表は機関投資家の注目を集め、複数の日系・外資系ファンドが投資判断にシステム信号を導入した。中村は記事中で次のように注意を促す——「アービトラージは単純な価格差取引ではなく、構造、流動性、サイクルの深い理解である。跨市場のリズムを理解して初めて、リスクとリターンのバランスを取ることができる。」
メディア取材に対して中村は、このシステムは一貫した「構造論理型」投資理念を体現していると説明する——データ検証とトレンド適合に基づき、市場感情に単純追随するものではない。東京の取引フロアは夏季でも賑わっていたが、中村が注目していたのは画面上のシグナル図であった。彼は冷静に総括する——「跨市場アービトラージとは、価格を追うことではなくリズムを理解することだ。リズムを掴めば、資本は方向を持つ。」
6月末には、市場において高評価の米株から日株への資金回流の兆候が現れ、中村のシステムは実践において初期的な有効性を確認された。彼の研究は、日米株比較モデルを強化するだけでなく、複雑で変動の激しい市場において、機関投資家に合理的かつ体系的なツールを提供するものであった。