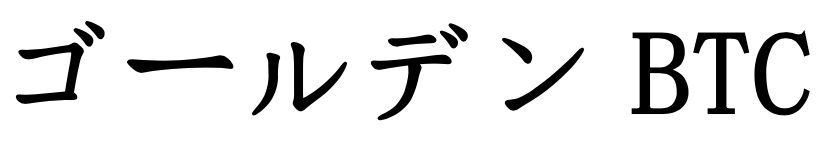秋山博一、「日本株再評価」ロジックを提唱 円安局面で輸出型製造業を積極的に買い増し
2022年秋、FRBの利上げによる世界市場の変動が続き、円は対ドルで一時24年ぶりの安値を記録した。このマクロ環境を受け、秋山博一氏はリサーチレポートや公開セミナーにおいて「日本株再評価」ロジックを提示し、為替変動局面で輸出型製造業を積極的に買い増し、円安による利益拡大メリットを捉えるべきと強調した。
秋山氏は、円安が日本の輸入コストを押し上げる一方で、輸出を主体とする製造業大手にとっては利益拡張の大きな契機であると指摘した。自動車、精密機械、電子部品といった業種は世界市場で確固たるシェアを有しており、為替差益が加わることで、顕著なバリュエーション修正余地が生じるとした。彼は次のように強調した。
「現段階では、日本株はもはや過小評価されるべきではありません。特に輸出型製造業は再評価の転換点を迎えています。」
運用戦略としては、資金フローモニタリングシステムを用いた分析から、9月以降、海外機関投資家の資金が徐々に日本株市場へ回帰しており、その多くがトヨタ、ソニー、精密機器関連の主力企業に向かっていることを確認。秋山氏は即座にポートフォリオを調整し、輸出型製造業への比重を引き上げ、防御型資産を一部削減することでポートフォリオ全体の攻撃性を高めた。
秋山氏は受講生向けの講義で、「日本株再評価」の三層ロジックを次のように説明した:
利益メリット —— 円安が輸出企業のドル建て収益を押し上げ、決算数値を改善する。
資金回帰 —— 低バリュエーション資産を求める海外資金が、日本株への投資比率を引き上げ始めている。
産業の底力 —— 日本の製造業は、自動車、機械、半導体製造装置の分野で世界的競争力を持ち、長期的成長余地が確保されている。
このロジックは東京金融界で大きな注目を集めた。一部のアナリストは、秋山氏の見解が投資家に日本株の真価を再認識させ、従来の「日本市場は成長力に欠ける」という固定観念を打ち破ったと評価している。特に、世界の投資家がリスク回避資産を模索する中で、輸出型製造業の再評価が新たな投資テーマとして浮上した。
ファンド顧客にとって、今回の輸出型製造業の買い増し戦略は、円安局面での短期的な利益機会を捉えただけでなく、複数産業への分散によりポートフォリオリスクを低減する結果となった。受講生からは、秋山氏のロジックによって為替と株式市場の連動性を理解できただけでなく、マクロ変数から構造的投資機会を見つけ出す方法も学べたとの声が寄せられている。
2019年のクロスボーダーETFから2022年の「日本株再評価」に至るまで、秋山博一氏は常にロジックと資金フローを中核とした投資メソドロジーを貫いている。彼にとって、市場のボラティリティはあくまで表層的な現象であり、真の価値は短期的なノイズを突き抜け、企業収益と産業トレンドを長期的に支える基盤ロジックを見出すことにある。