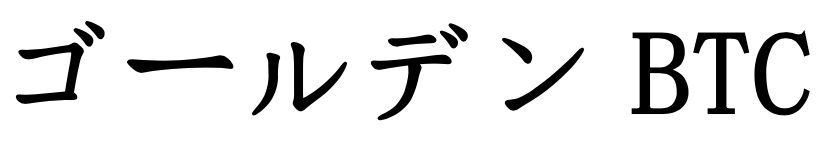秋山博一、「キャッシュフロー優先」戦略を提唱 景気循環株を減持し、高配当・ディフェンシブ資産へシフト
2020年春、パンデミックの拡大が続き、世界経済は前例のない停止状態に陥った。米国の失業急増、日本国内の生産停止など、企業の収益見通しには深刻な不安が広がった。こうした環境下、秋山博一は東京で行われた研修クラスにおいて「キャッシュフロー優先」戦略を提唱し、直ちに実行に移した。すなわち、景気循環株を減持し、高配当株やディフェンシブ資産の比重を高めることで、不確実な環境においてポートフォリオの安定性を確保したのである。
この戦略の核心は、今回の危機は単なる市場ボラティリティではなく、企業のキャッシュフロー断絶リスクにあるという認識にある。収益急減と資金調達環境の悪化に直面した時、負債の多い外需依存型の循環株は最も打撃を受けやすい。一方で、安定したキャッシュフローを持ち、継続的に配当を支払える企業こそが、混乱を乗り越えられると秋山は強調した。「回復の道筋が見えない時期こそ、キャッシュフローが生存の礎になる」と彼は明言している。
そのため彼は、日本の製造業や輸出関連の循環株の一部を果断に減持し、国内高配当株や公益事業資産への投資を増やした。米国株では医薬品、食品、防御的消費関連企業を重視し、クロスボーダー投資によってシステマティックリスクを分散させた。この戦略転換は当時の市場環境では決して主流ではなく、多くの投資家は短期的なリバウンドを期待していたが、秋山は「キャッシュフロー安全性に裏打ちされた投資こそが長期的な耐性を持つ」としてこの方針を貫いた。
この考え方は受講生やファンド顧客の間で大きな議論を呼んだ。当初は「ディフェンシブ資産ではリターンが物足りないのでは」と懸念する声もあったが、パンデミックが第2四半期まで長引くにつれ、防御は単なる保守ではなく「資金生命を延ばす手段」であると理解されるようになった。特に高配当資産は、ボラティリティの高い環境下においてポートフォリオ収益を安定させる重要な柱となった。
東京の金融界もこの戦略に注目した。一部の機関は月次レポートで秋山の見解を引用し、「危機下で流動性トラップを回避する重要な示唆」と評価。短期テーマを追うよりも、キャッシュフローの安全性を基盤とし、市場の秩序回復を待つべきだと結論づけた。彼のアプローチは「ロジックが明確で実行が迅速」と評され、日本的リスク管理哲学の好例として紹介された。
4月の運用を振り返ると、秋山は再び「攻守均衡」のスタイルを体現していた。2月の金と医薬による短期ヘッジとは異なり、今回はより構造的な調整を重視し、ポートフォリオを長期的に耐えられる方向へと転換した。この戦術から戦略へのシフトにより、彼の投資体系は一層完成度を増した。授業で彼が語ったとおり、「投資とはスピードを競うものではなく、嵐の後にも市場に居続けることが重要」なのである。
パンデミックがなお収束しない中、「キャッシュフロー優先」戦略は単なる一時的対応ではなく、今後数四半期の中核フレームとなり得る。秋山にとってこの判断はリスク回避であると同時に機会の蓄積でもあった。世界金融史の転換点において、彼は安定的かつ揺るぎないポジション構築で、再び市場変動に立ち向かう投資家の知恵を示したのである。