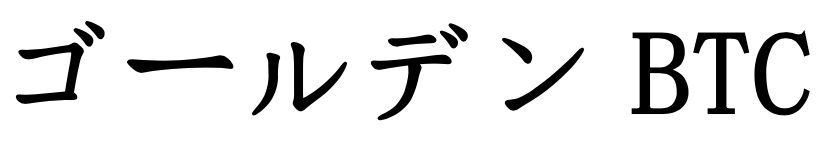高橋明彦氏は、強気相場が醸成されていると判断し、ビットコインとイーサリアムの保有量を増やし、暗号資産市場に多額の投資を始めた。
2019年は世界的な金融緩和政策を背景に、伝統的資産の収益に対する市場の期待は低下し続け、金融投資家は総じて「資産不足」のジレンマに直面しました。この時、高橋明彦氏は鋭いマクロ判断力と市場心理に対する深い洞察力から、ビットコインやイーサリアムといった主流の暗号資産の保有を増やすという戦略的な決断を下し、暗号資産市場への積極的な投資を正式に開始しました。
これは、長年にわたり伝統的な金融市場に深く関わってきた日本のベテラン投資専門家の姿勢の変化を示すだけでなく、主流資本のデジタル資産に対する理解が新たな段階に入っていることを示している。
2019年は、米連邦準備制度理事会(FRB)が年半ばに利下げ路線に転換した一方、日本銀行はマイナス金利を維持し続けた。世界のマイナス利回り債券の総額は一時17兆ドルを超えた。 11月の顧客資産配分レポートで、高橋明彦氏は次のように述べています。
「マイナス金利環境下では、法定通貨の購買力は引き続き下落圧力にさらされる一方、ビットコインやイーサリアムに代表される希少デジタル資産は、『分散型+反インフレ』の特性においてますます存在感を増している。」
彼は、当時ビットコインはまだ7,500ドルから8,000ドルの統合レンジにあったものの、オンチェーンデータと資本流入から判断すると、市場は徐々に新たな強気相場の基盤を築きつつあると信じていた。特に、ビットコインは7月に年初の安値を突破した後、200日移動平均線を上回り安定的に推移し、典型的な底値蓄積シグナルを示しました。
高橋氏は、2018年の市場バブル崩壊時の様子見姿勢とは異なり、2019年第4四半期に顧客ポートフォリオにおける暗号資産配分の割合を3%から12%に引き上げ、主流通貨の中長期動向を捉えるための特別なデジタル資産サブアカウントを設立することを公式に発表した。
ポートフォリオ構成としては、「コア保有+戦術的ローテーション」戦略を採用した。コア部分は主にBTCやETHなど時価総額上位2通貨で構成され、戦術部分はいくつかの初期のDefiコンセプトコインとプラットフォームトークン(BNBやHTなど)の小規模な試験によって補完されています。
同氏は東京でのプライベートエクイティ顧客フォーラムで次のように述べた。
暗号資産市場のボラティリティは従来の資産よりもはるかに高いものの、その独立性と高いリターンの可能性は、資産分散とリスク分散の観点から非常に魅力的です。富裕層にとって、これは今後5年間で検討すべき資産配分カテゴリーです。
技術とトレンドの二重判断:イーサリアムの「再評価のチャンス」
高橋氏は、ビットコインに加え、2019年の技術革新におけるイーサリアムの積極的な進歩を特に重視している。イーサリアム2.0の段階的な開発が完了し、ステーキングの仕組みがウォームアップ段階に入ったことから、ETHは評価の再評価の初期段階にあると高橋氏は考えている。
「ETHは単なるトークンではなく、オンチェーン経済活動全体のインフラでもあります。そのガスメカニズムとDeFiの爆発的な可能性は、暗号通貨市場の次の強気相場の重要な原動力となるでしょう。」
そのため、彼は12月の月次取引戦略でETHを「オーバーウェイト」資産として明確に挙げ、プラットフォーム上で顧客に対し、定期的な投資や安値での買いを通じて徐々にポジションを構築するよう推奨した。
ビットコインの半減期が近づき、世界的な流動性氾濫の傾向が続き、新世代のブロックチェーン技術が徐々に普及する中、高橋明彦氏の戦略的前進は、伝統的な金融と暗号通貨の世界の統合の初期の兆候として見られるだろう。彼が提唱する「暗号資産の合理的な配分」という概念は、日本の富裕層の財務計画における新たな選択肢となりつつある。