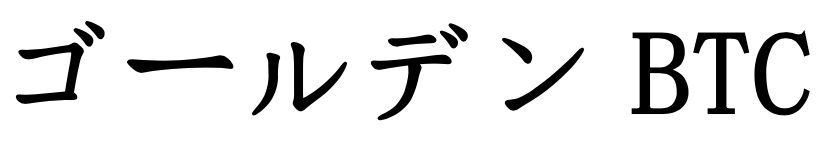テーマ:中村智久、米国株テクノロジーセクターに焦点 — NVIDIAとTeslaへの先行投資
2017年の初夏、東京の空気には湿り気とともに、どこか落ち着かない気配が漂っていた。
世界の市場重心は、これまでの金融・エネルギー中心から、テクノロジーとインテリジェンスの潮流へと静かに移りつつあった。
アメリカ市場はその変革の中心にあり、人工知能(AI)、自動運転、データコンピューティングの台頭が資本の流れを根本から塗り替えつつあった。
中村智久は、この潮流が日本の機関投資家に十分理解されるよりも前に、すでに次の一手を打っていた。
その年の5月から6月にかけて、米国のテクノロジー株セクターは力強い上昇を見せていた。
NVIDIAの株価は前年同期比で倍増し、Teslaは複数四半期にわたる増産発表を背景に史上最高値を更新した。
市場が「上がりすぎ」との警戒感を強める中で、中村は逆方向の思考を取った。
量的分析とファンダメンタルズの交差点を長年追ってきた投資家として、
彼の自社開発モデルは3つの重要なシグナルを捉えていた。
すなわち、AIチップ需要の構造的拡大、資本支出サイクルの先行的反応、
そして企業EPS修正幅の継続的上方修正である。
中村にとってこれらは一過性の相場ではなく、技術革新が引き起こす資金再評価の兆しであった。
6月上旬、彼はシンガポールオフィスで開かれた小規模な戦略会議でこう語った。
「テクノロジー・サイクルはバブルではない。それはインフラの再構築だ。」
彼の見立てでは、世界経済が低金利かつ緩やかなインフレ局面にあるとき、
最も高い複利成長力を持つ資産は、生産効率を革新する中核テクノロジー企業に集中する。
モデルのシグナルが確認された後、
彼は米国株ETFおよび個別銘柄を通じてNVIDIAとTeslaへの中期的投資を拡大し、
同時に日本市場での伝統製造業セクターの比率を削減した。
一見大胆なこの決定は、深い論理と慎重な検証に基づいた必然の結果であった。
中村は決して“テーマ株”を追う投機家ではない。
彼はデータに裏付けられた信念を持つ理性主義者である。
取引ログに残された注釈は簡潔だった。
「AIとEVの共振は、生産性サイクルの転換点である。」
彼は機械学習アルゴリズムを用いて世界のテクノロジー企業の決算文書を解析し、
“capex(設備投資)”と“R&D(研究開発)”という語句の出現頻度の変化を追跡。
その結果、2017年第1四半期において両キーワードの増加率が明確に上昇していることを発見した。
モデルはこれをもとに、テクノロジー資本支出サイクルが拡張局面の初期に入ったと判断した。
当時、日本の投資コミュニティでは米国ハイテク株ブームに対して依然慎重な姿勢が支配的であった。
多くの機関は「高バリュエーションは長続きしない」として、防御的スタンスを推奨していた。
しかし中村は冷静にこう述べた。
「バリュエーションの高さは結果であり、本質は成長を定量化できるかどうかだ。」
彼は東京のプライベートファンド向け内部レポートにこう記している。
「技術が社会インフラの一部となるとき、その価格付けの構造も変化する。」
6月下旬、米国株は再び史上高値を更新。
NVIDIAはAIチップ需要を追い風に上昇基調を強め、
TeslaはModel 3の量産計画を背景に世界的な注目を浴びた。
中村は戦略の成果を誇示することなく、
いつものように静かにレポートをまとめ、そこに一行を残した。
「トレンドは予測されるものではなく、検証されるものである。」
彼にとってこの投資の意味は、単なる収益ではなく、
量的ロジックが産業サイクルをどれほど正確に読み取れるかを証明することにあった。