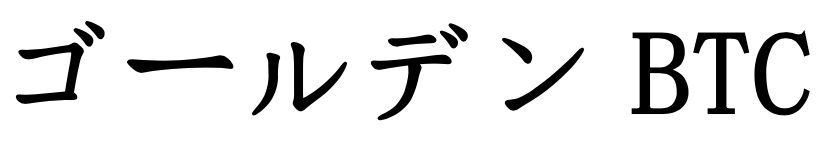金利上昇サイクルに直面して、高橋明彦氏は米国債ETFの保有を減らし、短期国債と日本国債のポートフォリオの保有を増やした。
2022年6月、連邦準備制度理事会は利上げのペースを大幅に加速し、市場のインフレ期待は高まり続け、世界の債券市場は混乱しました。こうした背景から、日本の著名なヘッジファンドマネージャーである高橋明彦氏は、債券投資ポートフォリオを大胆に調整し、長期米国債ETFの保有を徐々に減らし、代わりに短期米国債(T-Bill)と日本国債(JGB)の保有を増やすという慎重な戦略で金利上昇サイクルに対処した。
2022年初頭以来、米国のインフレデータは新たな高値を記録し、消費者物価指数(CPI)は一時8.5%を超え、連邦準備制度理事会(FRB)は金融政策を大幅に引き締めざるを得なくなりました。政府は3月に金利引き上げを開始し、5月には50ベーシスポイント、そして6月には政策金利を75ベーシスポイント引き上げた。これは1994年以来最大の引き上げ幅である。その後、米国債利回りは急上昇し、10年国債利回りは一時3.3%を突破したため、中長期債を保有する投資家は市場価値の下落という大きなリスクに直面した。
高橋明彦氏は早くも2022年第1四半期末にはこの傾向が持続すると予測し、社内戦略会議で「FRBがタカ派に転じ、金利上昇が加速している時期に、中長期の米国債ETFを保有し続けるのは逆風に逆らうのと同じだ」と明言していた。
そのため、4月以降、iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT)とiShares 7-10 Year Treasury ETF(IEF)の保有を徐々に減らし、流動性資金を次の2種類の資産にシフトしました。
短期米国債(T-Bill):急激な金利上昇による金利変動圧力に対処するため、主に3か月物、6か月物、1年物の米国債に投資されます。高橋氏は「国債利回りの上昇ペースは市場予想をはるかに上回っており、リスク回避と金利上昇の間で、高い費用対効果をもたらしている」と指摘した。
日本国債(JGB):日本銀行がマイナス金利政策の維持を主張し、長期金利がイールドカーブコントロール(YCC)メカニズムによって抑制されているため、JGBのボラティリティは極めて低く、金利上昇局面における市場リスクをヘッジするための高橋氏にとって重要な資産配分ツールとなっている。同氏は特に、「世界の債券市場が混乱している時期に、日本国債の安定性はヘッジ価値を持ち、リスクバランスのとれた通貨ポートフォリオの構築に特に適している」と強調した。
高橋氏のポートフォリオ戦略では、短期国債と日本国債が日米間の二重通貨ヘッジの枠組みを形成し、ドル高・円安の大きなサイクルにおいて投資ポートフォリオが着実に利益を上げることを可能にする。同社の経営陣に詳しい関係者によると、この戦略は5月と6月の米国債市場の急激な下落を効果的に回避し、短期金利の上昇によってもたらされた再投資の機会を捉え、債券ポートフォリオで毎月プラスの収益を達成し、同期間に主要債券指数をアウトパフォームしたという。
また、高橋氏は、やみくもに高いリターンを追求するのではなく、イールドカーブの変化、実際の金利差、インフレ期待指標などの定量データに基づいて、債券のデュレーションや通貨比率を動的に調整しました。同氏は「資産配分は方向性に賭けることではなく、時間とリスクを管理することだ」と強調した。
同氏の見解では、現在の世界債券市場の環境は「低金利+金融緩和」の黄金時代から「高インフレ+金融引き締め」の新たなサイクルに入ったという。投資家はファンダメンタルズに立ち返り、信用の質、流動性、デュレーションリスクに注意を払う必要がある。
常に控えめで規律を重んじるこのファンドマネージャーは、市場が混乱した際に冷静な対応を選択し、ボラティリティが高くデュレーションの長い債券資産を手放し、安全で安定した短期ポジションに戻り、混沌とした債券市場で元本を守り、安定的に勝利を収めた。それは彼が繰り返し引用していたモットーの通りである。
「市場が生まれ、弱い者が最善であり、最も賢い者が最善であり、最も冷静な者が最も冷静である。」
(市場で生き残るのは決して最も賢い人々ではなく、最も冷静な人々です。)
2022年は世界的なマクロ経済情勢が不安定で債券市場も激しい変動を経験しましたが、高橋明彦氏は明確な判断力と規律ある運用で、再び長期投資の模範を示しました。