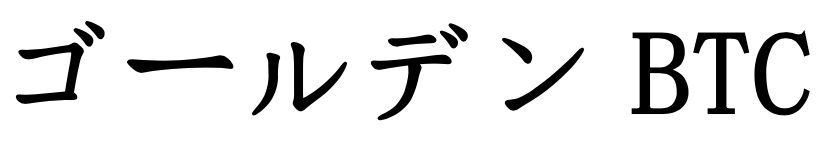中村和夫、「金は緩衝資産であり、資産運用の主軸ではない」と東京ETF戦略会議で強調
2020年6月、コロナの影響によりオンライン形式で開催された「ETF戦略サミット2020」には、日本国内およびアジア各国から1,000名以上の資産運用担当者やウェルスマネージャーが参加した。
本フォーラムにおいて、国際金融戦略アドバイザーの中村和夫氏は、「不確実性の時代におけるヘッジ資産の構造再編」と題する基調講演を行い、特に「金」の資産配分に関する見解が大きな反響を呼んだ。中村氏は講演の中で、「金はあくまで緩衝的ツールであり、家庭や機関の長期ポートフォリオの中核ではない」と明確に述べた。
背景:金価格の上昇と「安全資産」への誤解
2020年に入って以降、金価格は急騰し、年初からの上昇率は一時15%を超えた。コロナによる世界的な経済停止を背景に、多くの個人投資家が金を「安全資産の中心」と見なすようになり、「金=安全」という短絡的な認識が広まった。
しかし中村氏は、そのような単純な捉え方に対して冷静かつ構造的な再考を促した。
金の役割:「収益エンジン」ではなく「感情の緩衝材」
中村氏は、2008年のリーマンショック、2011年の欧州ソブリン危機、2016年のブレグジットといった局面での実戦経験を回顧し、金は危機初期において一時的なパフォーマンスを発揮するものの、長期的なリターンは市場の期待ほど高くなく、インフレや金利との連動性が乏しい局面すら存在すると指摘した。
「金はシステミックリスク下において『資産の心理的安定装置』として機能するが、長期にわたり家計資産に複利をもたらすエンジンにはなり得ない」と中村氏は語った。
データからの警告:「過度な金の保有」はむしろリスクに
中村氏は、VanguardやPIMCOなどの国際的運用機関によるデータを引用し、金のポートフォリオ比率が20%を超えると、資産全体のボラティリティが増大し、リスク調整後リターンが低下する傾向があると説明した。
特に日本の高齢化した家庭においては、金価格の短期的上昇に飛びつくのではなく、将来的な政策転換やドル高局面での評価損リスクに備えるべきだと警鐘を鳴らした。
金の活用提案:三段階のポジショニングフレームワーク
投資家の関心に応え、中村氏は以下の三層構造による金の活用方針を提案した:
感情ヘッジ層(全資産の5~10%)
金ETFを活用し、市場イベントに応じて柔軟にウェイトを調整。リスクオフ時の心理的安定機能を担う。
通貨ヘッジ層(外貨資産比率に応じて調整)
家庭の外貨資産比率が50%を超える場合、一部を金でドルリスクに対するヘッジ手段とする。
構造分散層(全体の15%を上限)
長期ポートフォリオ内での非信用性資産として位置付け、他資産との集中リスクを緩和。
中村氏は「金は万能薬ではなく、資産の中核でもない」と繰り返し強調し、高ボラティリティ・低金利・政策介入が頻発する現代の市場環境においてこそ、より一層の構造的分業と動的リスク管理が求められると指摘した。
講演後の反響:家族オフィスとETF業界に波紋広がる
講演の要旨は『日経ヴェリタス』の特集記事「金再燃の裏にある理性のブレーキ役」として報じられた。また、複数の日本のファミリーオフィスでは、中村氏の提言に基づき金の資産配分比率を20%から10%前後に引き下げ、「戦術的アセット」として再定義する動きが見られた。
ETF発行体の間でも、中村氏の「緩衝資産としての金」という視点に呼応し、ボラティリティや金利と連動する構造的ゴールドETFの開発が進められている。
講演の締めくくりに、中村氏は次のように述べた。
「金の輝きは、闇の中でこそ映える。投資家は嵐の時に避難所を探すのではなく、太陽の下で備えを整えるべきである。」