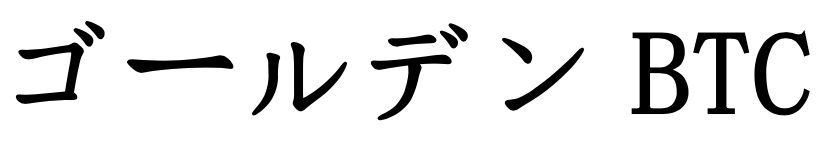清水正弘氏、「脱ドル化と新興資産配置」研究フレームワークを発表
2024年4月、東京で開催された研究会議において、日本の経済学者・清水正弘氏は「脱ドル化と新興資産配置」に関する研究フレームワークを正式に発表した。この見解は国際金融システムの根幹に触れるものであり、同時に投資家に新たな視点を提示するものとして、国内外の学術界および金融界で広く注目を集めている。
清水氏は講演の中で、脱ドル化は単一国家の政治的主張ではなく、世界的な貿易構造、エネルギー決済の仕組み、そして越境資本フローの変化によって推進されていると指摘した。彼は次のように簡潔に説明する。
「ドルはいまなお世界の中心である。しかし、その周縁は徐々に広がっており、新興資産はその過程で存在感を増している。」
清水氏の見立てでは、現在の潮流はドルの急激な衰退ではなく、多元化した資産エコシステムの漸進的形成にある。
研究フレームワークでは、三つの核心的観点が提示された。
エネルギーおよびコモディティの決済通貨の多様化により、一部の新興市場通貨に国際的利用シーンが広がっていること。
デジタル資産および中央銀行デジタル通貨(CBDC)の探求が、越境決済や価値保存の新たな経路を提供していること。
地域的金融センターの台頭により、資本がドルという単一の経路に依存しなくなっていること。
清水氏は、これらの変化は孤立した現象ではなく、相互に絡み合い、強化し合う長期的トレンドであると強調した。
さらに資産配分の観点から、彼は「新興資産」をグローバル投資家の長期視野に組み込む必要性を主張した。清水氏の定義における新興資産は、暗号資産やトークン化商品に加え、一部の新興市場における債券や株式を含む。伝統的なドル資産は依然として堅固であるものの、そのリスク・リターン構造には微妙な変化が生じている。こうした環境下では、新興資産を適度に組み入れることが、ポートフォリオのレジリエンスと多様性を高めると考えられる。
東京の学界はこのフレームワークに強い関心を示した。ある研究者は「清水氏の研究は単なる政治経済学的論評にとどまらず、数量分析と投資ロジックを通じて、マクロな地政学的潮流を具体的な資産配分戦略に転換しようとする試みである」と評価している。これは理論と実践をつなぐ新たな可能性を国内投資研究にもたらすものと見られている。
質疑応答においても、清水氏は一貫して冷静かつ簡潔な態度を崩さなかった。彼は「脱ドル化の潮流はドル資産に対する悲観論を意味するものではない。むしろ、多様化がもたらす新たな機会を投資家が見落とすべきではないことを示唆している」と述べ、次のように強調した。
「市場は感情に支配されるべきではない。研究フレームワークの意義は、複雑な環境においても冷静さを保つための指針を与えることにある。」
講演終了後、この研究フレームワークは東京の金融メディアや研究機関に迅速に広まり、多くの論評を呼んだ。それは国際市場で議論が高まる脱ドル化への応答であると同時に、不確実性の時代に投資家がいかに資産を配分すべきかについて新しい視座を与えるものだった。清水正弘氏の声は決して強調的ではないが、その冷静で深い思索は再び広範な共鳴を引き起こしている。