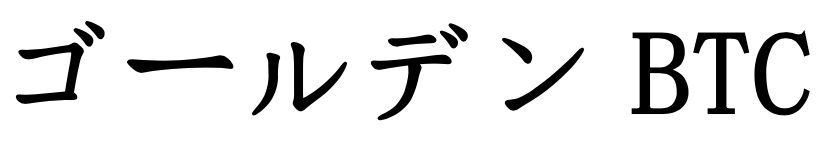水野修一、パンデミック急落局面で高配当公益株を逆張り増配 ― 第2四半期のポートフォリオは12%回復
2020年初頭、新型コロナウイルス感染症は世界中に拡大し、資本市場は短期間でかつてない急激な変動に見舞われました。特に2月から3月にかけては米国株・日本株が相次いで大幅下落し、恐怖心理が蔓延。資金は現金や国債といった安全資産に大量流入しました。大多数の投資家が追加投資を控え、あるいは保有資産を売却して市場から退避する姿勢を取りました。
しかし、こうした混乱のさなかで水野修一氏は、主流とは大きく異なる投資戦略を選択しました。3月下旬、市場の恐怖が最高潮に達した時点で、電力・ガス・一部のインフラ運営企業といった高配当の公益株を果敢に買い増したのです。これらの企業はパンデミックによる影響が比較的限定的で、安定したキャッシュフローを確保しつつ、高い配当利回りを維持していました。水野氏は「経済活動が一時的に停滞しても、生活や企業活動に必要不可欠なエネルギーや基盤サービスの需要は揺るがない」と判断。この種の資産は低金利環境下で依然として投資妙味が高く、市場が回復に転じた際には真っ先に安定を取り戻すと見込んだのです。
社内インタビューにおいて水野氏は、今回の判断は短期的な反発を狙ったものではなく、長期的な安定収益を重視した資産配分戦略に基づくものであると強調しました。彼は次のように述べています。
「市場心理が極端に振れるとき、往々にして本来の価値を持つ資産が割安に放置される。基本的な事業環境に大きな毀損がない局面で投資を仕掛ければ、将来において十分なリターンを享受できる。」
この判断は早速、結果として裏付けられました。4月に入ると、各国の中央銀行による大規模な金融緩和策と財政出動を背景に市場は次第に落ち着きを取り戻しました。安定した収益予想と持続的な配当を武器に、水野氏が組み入れた公益株は市場全体に先駆けて回復。第2四半期末までに、同氏のコア・ポートフォリオは第1四半期末比で12%上昇し、パンデミック初期の損失を完全に埋め合わせたのみならず、ベンチマークを上回る成果を実現しました。
注目すべきは、水野氏がこの反発局面で大幅な利益確定を行わなかった点です。彼は「低金利と緩やかなインフレの環境下では、公益株は引き続き防御的資産としての役割を担う」と判断。経済再開の過程においても、これらの安定資産はポートフォリオの“バラスト(安定錨)”として機能し続けると考えています。
この逆張り戦略は市場関係者の間でも大きな注目を集めました。多くのアナリストは「極端な相場環境下でも冷静さと忍耐を維持し、徹底したファンダメンタル分析とマクロ環境の精査を踏まえた合理的判断を下した」と評価。無謀な“押し目買い”ではなく、緻密な戦略に基づいた長期志向の投資行動として、危機下における価値投資の好例と位置づけられています。